家が沈んだ! -それは、地盤が軟らかかったから-
たしかにその通りです。まさに、このような地盤を「軟弱地盤」と呼ぶわけですが、もう少し詳しく説明しましょう。
「軟弱地盤」の上に建物を建てると、基礎下部の土が建物の圧力に屈し、移動してしまい、そのために建物が沈んでしまうのです。(例えば、豆腐を例にとってみましょう。豆腐を手で押さえつけると 豆腐が崩れ、動き始めた豆腐は指と指の間からグンニャリ出てきて、手が沈みます。この時の豆腐が地盤で手が建物だとイメージしてください。)
しかしその一方、仮にそんな地盤であっても、上に建つのが非常に軽い建物であったら、柔らかい土でも動かず、従って建物は沈みません。
つまり、「軟弱地盤」とは建物と常に相対的に考えられるもので、建物の重さに耐えられるだけの地盤の強さ(地耐力)が不足している場合に、特に指していうのです。
|
 穴を掘って埋め戻したり、土を盛ったりなど人工的に手が加えられた地盤は全部、危ない地盤と思っていただいて結構です。これはもう、一目瞭然!周辺と土の色が違っていたり、地面から直角に立ち上がっている擁壁を見たら要注意。「軟弱地盤」と思っていただいて、まず、間違いありません。 穴を掘って埋め戻したり、土を盛ったりなど人工的に手が加えられた地盤は全部、危ない地盤と思っていただいて結構です。これはもう、一目瞭然!周辺と土の色が違っていたり、地面から直角に立ち上がっている擁壁を見たら要注意。「軟弱地盤」と思っていただいて、まず、間違いありません。
 道路の真ん中や少し小高い場所に立って、周辺を見渡してください。わずかな傾斜も見逃さず、地形の高低を把握しましょう。「軟弱地盤」のひとつの要素に、水を含んだ地盤があげられます。水は高きから低きに流れ、低きに至り留まります。水の留まるところが最も軟弱なのです。また、湿地になっているケースも多く見られ、比較的背の高い草が生い茂っています。 道路の真ん中や少し小高い場所に立って、周辺を見渡してください。わずかな傾斜も見逃さず、地形の高低を把握しましょう。「軟弱地盤」のひとつの要素に、水を含んだ地盤があげられます。水は高きから低きに流れ、低きに至り留まります。水の留まるところが最も軟弱なのです。また、湿地になっているケースも多く見られ、比較的背の高い草が生い茂っています。
|
やはり、水の存在や低いところを意昧する地名がつけられた場所は、「軟弱地盤」が多いといわれています。
- サンズイの付いた地名
- 池・沼・沢・汲・渋・溝・洲・潟・泥
- 水にまつわる地名
- 田・稲・川・橋・水
- 水鳥の名の付いた地名
- 鶴・鴻・鷺・鴨
- 低い場所を示す地名
- 谷・窪・下
|
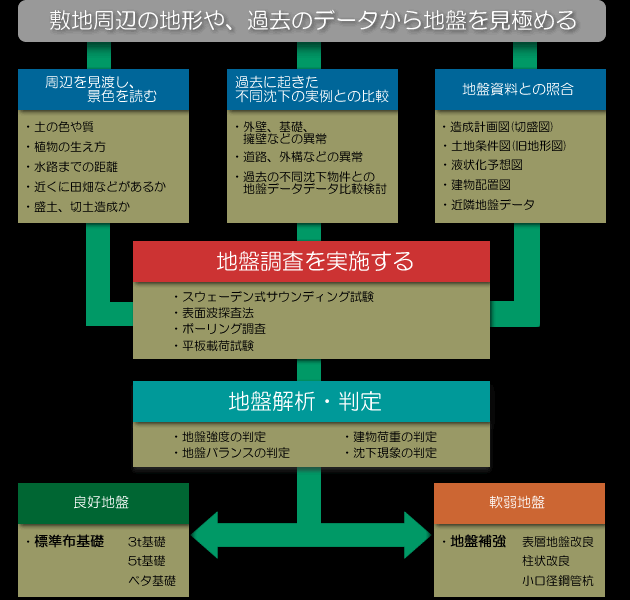
|
  |